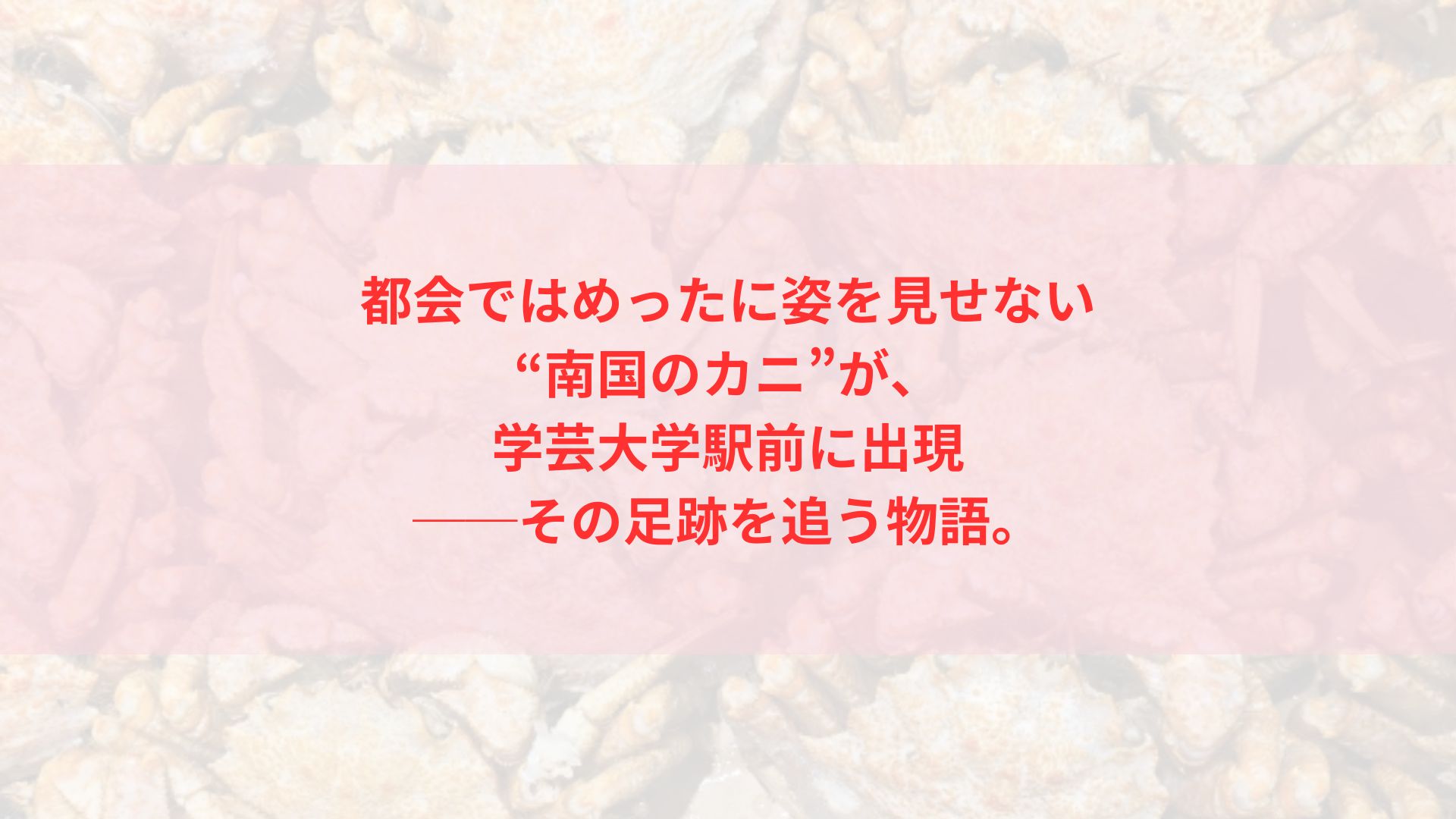都会の歩道を横切る、話題の“珍客”

2025年8月初め、SNSで注目を集めたのは、東京・目黒区の学芸大学駅周辺で撮影された短い動画でした。
映像には、ビルや住宅に囲まれた歩道を、カニがのんびりと横歩きする様子が収められています。
通勤や通学で人通りの多いエリアだけに、その場違いな光景はネット利用者の笑いと驚きを誘いました。
「サンマの次はカニが目黒に?」といった冗談も飛び交い、動画は瞬く間に拡散されます。
深夜に初めて確認された正体不明のカニ

最初の目撃は6月28日深夜。
駅から少し離れた車道脇を歩く姿を通行人が見つけ、スマートフォンで撮影しました。
この映像がSNSで広がると、専門家が分析を開始。
甲羅や脚の形から、南国に生息する「ミナミオカガニ」の可能性が高いと判明します。
ミナミオカガニは沖縄や先島諸島など温暖な海岸に暮らす陸生のカニで、都心で見られることは極めて珍しい種です。
ミナミオカガニの特徴
- 生息地:琉球列島(沖縄本島・宮古島など)の砂浜や海辺
- 生活:普段は陸上で暮らし、海へ戻るのは卵からふ化した幼生期のみ
- 行動:夜行性が強く、日中に出歩くことは稀
住宅街で見つかったのは極めて異例のケースです。
1か月後に別のカニも?
さらに7月26日夜、駅から少し離れたコンビニ前で新たなカニが発見されました。
6月の個体はすでに保護されて別の場所で飼育されていたため、今回のは別個体とみられます。
この地域に複数のカニがいる可能性が浮上しました。
なぜ南国のカニが東京に?

考えられる理由は大きく3つあります。
ペットの逃走・遺棄
都内には熱帯性の甲殻類を扱うペットショップも多く、観賞用の珍しいカニが販売されています。
飼育環境の破損や飼い主による放棄で外に出た可能性があります。
人に慣れている様子からもこの説が有力です。
貨物に紛れ込んだ
南西諸島から運ばれた観葉植物や石材などに幼体が入り込み、本州へ届くことがあります。
ただし今回の個体は成体だったため、この説には疑問も残ります。
飲食店説は否定
「飲食店から逃げたのでは」との声もありましたが、地元の店舗は生きたカニを扱っていないと回答し、この説は早期に否定されました。
食用には向かない?
香りは良いが味は淡白
沖縄在住のライターによれば、塩ゆですると香りはよいものの、味は薄く土のような風味が強いとのこと。
可食部が少ない
食べられるのは主にハサミの白身部分だけで、脚や胴体の身はわずか。
殻も硬く調理に手間がかかります。
ミソは泥臭い
泥抜きしてもえぐみが残るため、食材としての価値は低いとされます。
総じて「観察向きで食用には不向き」という評価です。
都市で出会う意外な生き物たち

- 荒川河川敷:クロベンケイガニが集団で歩道を横断
- 文京区の湧水:サワガニが定着
- 江戸川・浦安沿岸:ベンケイガニ類の生息確認
- 東京湾:熱帯魚やサンゴが繁殖
- 公園:ワカケホンセイインコが桜を食害
都市でも自然との接点は確実に増えています。
ネット上の反響
SNSでは「目黒にカニ!?」と驚く投稿が続出。
YouTubeでは速報動画が数十万回再生される一方、「冬は越せないのでは」「早く保護を」と心配する声も多く見られました。
専門家が考える3つの仮説
| 仮説 | 根拠 | 情報源 |
|---|---|---|
| ペット逃走説 | 人慣れした行動、専門店での流通 | FNNほか |
| 貨物混入説 | 園芸品などに紛れ込む可能性 | 国立科学博物館 |
| 気候変動説 | 東京湾で熱帯魚やサンゴが定着 | 各種調査 |
現時点では「ペット逃走説」が最も有力ですが、複数の要因が重なっている可能性もあります。
遭遇したときの対応

- 直接触らず距離を取る
- 写真や動画で記録(位置情報つき)
- 自治体や動物愛護センターへ報告
- 一時保護は日陰で管理
- 無断で飼育しない
まとめ
学芸大学駅前のカニ騒動は単なる珍事件ではなく、
- 人と野生生物との距離感
- ペットや物流管理の課題
- 温暖化による都市生態系の変化
といった問題を映し出しました。
一匹のカニが、都市と自然の関係を考えるきっかけとなったのです。